 |
(31)『まぼろしの小さい犬』 (ピアス作、猪熊葉子訳、岩波書店、1890円) 誕生日に犬がもらえると期待していたベンは、かわりに送られてきた小さな犬の絵に失望する。でも、ロンドンで犬を飼うのはたしかにむずかしい。現実の壁が理解できる年頃になっただけに、ベンは傷ついた心を隠し、やがてその心のなかで、目を閉じたときにしか見えない小さな犬を飼いはじめる。空想のなかで大活躍する犬に夢中になったベンは、しだいに現実に背をむけるようになっていく。 子どもが現実と折り合いをつけながら生きることを学ぶのは大仕事で、温かい家族のなかにいることが、かえって重荷になることもある。しかし、いざというときにしっかりと支えてくれるのは、やはり家族だ。特に、無骨な祖父と厳しい祖母の大きな愛は、ベンと悩みや喜びをともにした読者にとっても、忘れがたいものとなることだろう。(2004.12.12) |
 |
(32)『ドヴォルジャーク』 (黒沼ユリ子作、リブリオ出版、1575円) チェコの人たちは音楽好きで、一日の労働を終えたあと、楽器を弾いてみんなで楽しむ。だから、肉屋の息子のトニークがヴァイオリンを習うのも、あたりまえだった。でもトニークには、本物の才能と音楽への深い愛があった。肉屋の修行のかたわら、苦労して音楽の勉強を続けたトニークは、やがて作曲家として大成功をおさめた。それが交響曲『新世界より』やチェロ協奏曲で名高いドヴォルザークだ。 この伝記は、ドヴォルザークが好きでチェコに留学したヴァイオリニストである著者が、熱心に資料を集め、精魂こめて書き上げた力作だ。地方色豊かな生活ぶりや社会情勢のこともていねいに書かれており、読んでいると、音楽というものの大きな力がわかるとともに、チェコという国が大好きになってくる。(2004.12.12) |
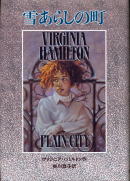 |
(33)『雪あらしの町』 (ハミルトン作、掛川恭子訳、岩波書店、2100円) 蜂蜜色の肌をしたブレアは、独立心の強い少女。ナイトクラブで歌っているお母さんはすてきな女性だが、めったに家に帰ってこない。ある日、死んだはずの父親が生きていると知ったブレアは、家を飛び出し、雪嵐のなかで遭難しかかったところを、ずっとあとをつけていた父親に助けられる。ところが父親はホームレスで、精神状態も少しおかしい。 十二歳ごろというのは、急に自分の心のなかが見えはじめ、そこでせめぎあういろんな思いにふりまわされながら、少しずつ自分という人間をつかんでいく時期だ。ハミルトンは、まるで少女の心のなかをのぞきこんでいるかのような語り口で、傷つきながらも成長していくことの喜びを実感させてくれる。ブレアの成長とともにちがった顔を見せはじめるまわりの大人たちも魅力的だ。(2004.12.26) |
 |
(34)『少年動物誌』 (河合雅雄作、福音館書店、735円) 著者はサルの研究で名高い動物学者。これは、丹波の篠山ですごした少年時代に、すぐ下の弟と二人で動物を飼ったり、魚を獲ったり、藪を探険したりした思い出の記だ。動物を飼うといっても半端ではなく、モルモットを飼えば増えすぎて、冬には餌を集めるのに大変な苦労をすることになる。両親はおおらかに見守ってくれるが、自分の好きなことは自分の力でやれと言って、援助はしてくれない。だから子どもたちは、必死で知恵をしぼり、全身全霊でぶつかっていくことになる。 少年にとって、自然は単なる観察の対象ではなく、空想や恐れ、つかみどころのない悲哀など、さまざまな思いを受け止めてくれるものでもあった。自然とのそんな絆の深さが、昔なつかしい暮らしの記録を、詩のように格調高いものにしている。(2004.12.26) |
 |
(35)『九つの銅貨』 (デ・ラ・メア作、脇明子訳、福音館書店、683円) デ・ラ・メアは子どものための詩で名高いイギリスの詩人。だから、物語にも詩のような香気と、独特の味わいがある。この短編集には五つのお話が含まれているが、おとぎ話でおなじみの妖精や小人、人魚などが、本当にそんなものを見てしまったときの驚きをこめて描かれているので、「不思議」という感覚を原点にもどって味わい直すことができる。 でも、もっと不思議なのは、デ・ラ・メアの言葉にそって想像力を働かせていると、子ども時代の小さな記憶が、光の感じや草木の匂いもそのままに、ふっとよみがえってくることだ。それは作者自身が、子どもの感覚でとらえた世界を詩人ならではの言葉で語ってくれているからで、子どもが読めば、自分の感じていることを見事にとらえた言葉の魔法に、驚きと喜びを味わうだろう。(2005.1.9) |
 |
(36)『雪は天からの手紙』 (中谷宇吉郎作、岩波書店、756円) この詩的なタイトルは、雪の結晶の研究者であった著者の、とても有名な言葉だ。意味は、雪の結晶の形を見れば、上空の気温、湿度、風など、いろんな情報が読み取れるということ。著者は北大に低温研究室を作り、そこで自由自在に雪の結晶を作ってみせて、その理論を証明した。 このエッセイ集には、著者の専門の雪や氷、霜柱、雷などの話はもちろんのこと、線香花火、茶碗の湯からたつ湯気、卵が立つかどうかという問題などが取り上げられている。どれも、ふつうの生活で出会うこと、だれでもすぐに観察したり試したりできるようなことだが、それを出発点に科学的な考察を深めていくことが、どれほどわくわくする知的冒険であるかということがよくわかる。優れた観察眼は人間にも及び、先輩の物理学者たちや山小屋の番人などを語る言葉も忘れがたい。(2005.1.9) |
 |
(37)『雪女 夏の日の夢』 (ハーン作、脇明子訳、岩波書店、714円) 「耳なし芳一」や「雪女」などの怪談で知られる、ハーンこと小泉八雲は、明治時代の中ごろに取材旅行のつもりで日本を訪れ、気に入ってそのまま住み着いてしまった人だ。この短編集におさめられた作品の大半は、日本の古い物語を語り直したものだが、想像力豊かな異国の人の目を通すことで、格調高くて神秘的な独特の味わいが加わっている。 それにも増しておもしろいのが、日本の印象を語る四編のエッセイ。ハーンが目を見張り、心を奪われた風俗は、私たちの記憶の片隅に残ってはいても、もはやほとんど目にすることのできないものだ。ハーンの魔法によっていきいきとよみがえった過去の世界を目にする喜びに、こんなにも美しいものを失ってしまったという悲しみが混じって、まるで不思議な夢を見たような深い余韻が残る。(2005.1.23) |
 |
(38)『雪の夜に語りつぐ』 (笠原政雄語り、中村とも子編、福音館書店、893円) 雪国の冬の長い夜、大人はせっせと手仕事をしながら、子どもたちに昔話を語って聞かせたものだ。この本の語り手、笠原さんも、お母さんの昔話を聞いて育った人だ。好きで好きでたまらなかったお話は、わざわざ覚えようと思わなくても自然に頭と心にしみついていて、四十をすぎてふとしたことから語りはじめてみたら、たちまち百をこえるお話があふれ出てきて、自分でもびっくりしたそうだ。 この本には、笠原さんの子ども時代の思い出話が、新潟弁で語られる七十ほどの昔話とともに収められている。思い出話を先に読めば、方言にも自然に慣れて、笠原さんがお母さんから受け継いだ温かい語り口こそが、昔話のいのちであることがよくわかる。いま私たちになによりも必要なのは、こんな親子のつながりを取りもどすことではないか。(2005.1.23) |
 |
(39)『ゆうかんな女の子ラモーナ』 (クリアリー作、松岡享子訳、学習研究社、945円) 六つのラモーナは自分のことを、勇敢で怖いものなしの女の子だと思っている。たったいまも大きな男の子たちに立ち向かい、からかわれている姉さんを守ってあげた。ところが姉さんは、恥ずかしかったと怒っている。姉さんから見たラモーナは、へんなことをする小さい子にすぎないのだ。心のなかではなんだってうまくいくのに、やってみると期待と現実は大ちがい。学校でも家でも、おかしなさわぎを引き起こしてばかりだ。 両親も姉さんも先生も、温かくてすてきな人たちなのだが、子どもの気持ちというのは自分でもわからないくらい複雑で、なかなか理解してもらえない。でもラモーナは、へこたれずに新たな夢をふくらませ、少しずつ自分の気持ちをつかんでいく。主人公より少し大きい子どもたちに読んであげれば、「自分もそうだった」と深く共感できるだろう。(2005.2.13) |
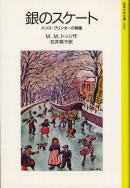 |
(40)『銀のスケート』 (ドッジ作、石井桃子訳、岩波書店、630円) いたるところに運河があって、冬に全部が凍ったら、スケートで町から町へ旅ができたという昔のオランダ。貧しい兄妹ハンスとグレーテルを主人公に、事故でずっと意識不明のお父さん、消えたお金の謎、賞品に銀のスケートがもらえるスケート大会などの話が綾をなし、最後にはもつれた糸がするするとほどけて、心温まるハッピーエンドがやってくる。がんこで名高いお医者さんがお父さんを治してくれて、それがお医者さんにも幸せをもたらす展開は感動的だ。 ハンスより裕福な少年たちがスケート旅行に出かけ、泊まった宿で泥棒をつかまえる痛快なエピソードもあり、帆かけのそりなども走っていたオランダの運河の景色が目に見えるようだ。児童文学の古典ちゅうの古典で、挿絵も見れば見るほど味わい深い。(2005.2.13) |