 |
(21)『グリーン・ノウの子どもたち』 (ボストン作、亀井俊介訳、評論社、1500円) 冬休み、小さな少年トーリーは、たった一人で汽車に乗って、ひいおばあさんの家をたずねる。大雨で水びたしになった駅から、ボートに乗ってたどりついた家は、大きな庭にかこまれた石作りの古い屋敷で、まるでノアの方舟のよう。はじめて会ったひいおばあさんは、トーリーのことをとてもよくわかってくれて、二人はすぐなかよしになる。 ひいおばあさんは、昔その家にいた子どもたちのことを話してくれるが、やがてトーリーは、あちこちにその子たちの気配があることに気づき、かくれんぼの鬼になったみたいに、その子たちを探してまわる。時間を忘れたようなおだやかさに満ちた、不思議で、しかも温かいクリスマス物語である。(2002/12/15) |
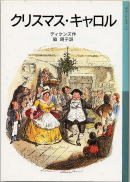 |
(22)『クリスマス・キャロル』 (ディケンズ作、脇明子訳、岩波書店、640円) クリスマスといえば、だれもが思い浮かべるのは、楽しくてうれしいことばかり。ところが、この物語の主人公スクルージは、けちでがんこな年寄りで、クリスマスを祝う気なんか少しもなかった。ところがそのスクルージの陰気なすまいに、風変わりな幽霊たちが出現し、過去と現在と未来の世界へ次々に案内してくれる。 少年時代の思い出に涙し、町のにぎわいに浮かれ、貧しくても温かいクリスマスの集いに夢中になり、このままだとどんな未来が待っているかを思い知ったスクルージは、「クリスマスの本当の祝い方を知る人」へと大変身。イギリスの文豪による古典的傑作だが、ユーモアと活気に満ちていて、クリスマスが大好きになることうけあいだ。(2002/12/15) |
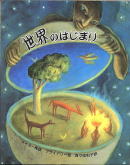 |
(23)『世界のはじまり』 (メイヨー再話、百々佑利子訳、岩波書店、1900円) この世界はどうしてこうなんだろう。なぜ太陽はあんなにまぶしく光り、夜はこんなに暗いのだろう。なぜ人間は永遠に生きられないのだろう。私たちはもはやそんな素朴な疑問を忘れ、どんな疑問にも科学が正しい答えを出してくれるものと思っていはしないだろうか。 だが科学の答えは、正確ではあってもクールすぎて、子どもたちの心を落ち着かせてくれはしない。それに対して、この本に集められた世界の諸民族の創世神話は、現実離れしていながら物事の本質をあざやかにとらえ、温かい人間的な言葉で語ってくれて、根無し草になりかかった心に、根を生やす土台を与えてくれる。ブライアリーによる骨太な挿絵も、神話の豊かなパワーをしっかりと受け止めている。(2003/1/5) |
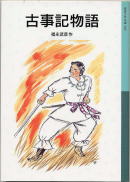 |
(24)『古事記物語』 (福永武彦作、岩波書店、720円) みなさんは、海幸と山幸の物語や、オオクニヌシとスセリ姫の物語をごぞんじだろうか。日本最古の書物である『古事記』は、私たちの祖先が口伝えで保存してきた神話や伝説や歴史をまとめて記録したものだが、そこには、日本にもこんなお話があったのかと驚くほど、スケールの大きな物語が詰まっている。 神話はともすると政治的に利用されやすく、日本神話も軍国主義と結びついてきたために、戦後は敬遠され、いつしか忘れられてしまいつつある。しかし、世界のさまざまな文化のなかで、私たちがどういう位置にいるのかを知るためにも、無意識の底にある自分たちの神話を見直すことは必要だ。原文の味をいかした福永氏の再話は、大人にとってもありがたい神話入門である。(2003/1/5) |
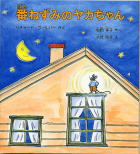 |
(25)『番ねずみのヤカちゃん』 |
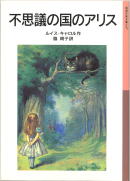 |
(26)『不思議の国のアリス』 |
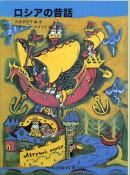 |
(27)『ロシアの昔話』 |
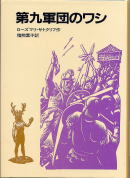 |
(28)『第九軍団のワシ』 |
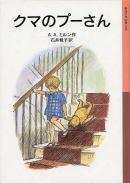 |
(29)『クマのプーさん』 |
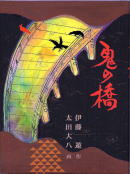 |
(30)『鬼の橋』 (伊藤遊作、福音館書店、1400円) 日本の児童文学には、まだ無国籍でない本格ファンタジーは少ないのだが、これは新しい道をひらいた傑作だ。舞台は平安初期の京都で、主人公は実在の人物、小野篁。ただし、物語のなかではまだ十二歳の少年で、事故で妹を死なせた自責の念から、黄泉の世界へ迷いこむ。 題名の橋は、黄泉の世界の三途の橋であり、現実の世界の賀茂川にかかる橋でもある。その二つの橋を行き来しながら、少年は勇ましいホームレスの少女や、片角をなくして半ば人間化した鬼など、さまざまな者たちに出会い、自分の非力さを思い知らされながらも、少しずつ生きる力を養っていく。骨太な歴史ファンタジーでありながら、現代の少年少女の切実な悩みを受け止めることもできる作品だ。(2002/2/16) TOP |