 |
『感情体験をさせてくれる物語』 2006年5月13日(会報第40号) ゴールマンの『EQこころの知能指数』と感情体験の大切さ(脇)/ その観点から選ばれた絵本と物語の事例を交えての紹介 『あーんあん』『コッコさんのともだち』『しょうぼうじどうしゃじぷた』 『時計つくりのジョニー』『やかまし村の春夏秋冬』 『大きな森の小さな家』『人形の家』 |
 |
『五感体験、感情体験をさせてくれる物語』 2006年7月29日(会報第41号) 感情体験や五感体験の重要性と本の力について(脇)/ その観点から選ばれた本の紹介 『があちゃん』『コッコさんのかかし』『グレイ・ラビットのおはなし』 『白鳥』『思い出のマーニー』『秘密の花園』 |
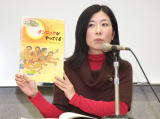 |
『男の子の心をつかむ物語』 2006年12月16日(会報第43号) テーマについての話(脇) 感情体験が重要なのに、小学生は視覚に訴える本や刺激の強い本に引きつけられがち。特に発達上の問題をかかえた子どもや男の子にその傾向が強く、だからこそ男の子を満足させる力のある、おもしろくて質のいい物語が必要。/ 保育園や小学校での興味深い事例を交えながらの本の紹介 『オンロックがやってくる』『サラダとまほうのおみせ』 『狼森と笊森、盗森』『ロシアの昔話』『ちびっこカムのぼうけん』/ 『王への手紙』の紹介と、朗読を交えての『雪女 夏の日の』の紹介 |
 |
『小学生への読み聞かせと読書について』 2007年7月21日(会報第46号) テーマの説明(脇) 小学生への働きかけの現状。子どもが自分で読み始めると速読に走りやすく、「たくさん読みなさい」という指導も、子どもを速読に追いやる。速読では感情体験、五感体験はできず、思考力も働かない。極度に刺激的な内容の本が好まれるのも速読のせい。読み聞かせは速読を防ぐためにも有効。/ 小学生に読み聞かせるのにお勧めの本の、朗読を交えながらの紹介 『小さな山神スズナ姫』『西遊記』『鬼の橋』 『魔法使いのチェコレート・ケーキ』 |
 |
『本を選ぶ目を養うために(一)』 2007年12月22日(会報第47号) 絵本を中心に、いま読み聞かせなどでよく取り上げられるけれどもあまりいいとは思えないものを取り上げ、似た題材の本当にいい絵本と比較しながら、どこがどう問題なのかを具体的に見た。 比較に使った本のうちおすすめのものは、『わたしとあそんで』 『だくちるだくちる』『ちょっとだけ』/ 遊園地的世界観とカーソン的世界観の違いと本の比較(脇) 紹介された本のうちおすすめのものは、『氷の花たば』 『シートンの「動物記」』『ふわふわふとん』『よあけ』『えぞまつ』 |
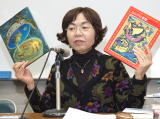 |
『本を選ぶ目を養うために(二)』 2008年2月2日(会報第48号) 昔話の本や絵本を取り上げた。 『物語が生きる力を育てる』の紹介と、昔話の選書のポイント(脇)/ 『おおきなかぶ』の比較/ 『三びきのこぶた』の比較と、『「わらべうた」で子育て』/ 『わらしべ長者』の比較/ 『ねことおんどり』の保育園と小学校での読み聞かせと感動的なエピソード |
 |
『メディア教育と読書』 2008年6月30日(会報第51号) 米子市の小学校でのメディア教育とその成果(ゲスト:米子市の小学校教頭の舩越晶子さん)/ 雨や風などお天気を感じることができる本の紹介 (都市部でもできる五感体験) 『かぜフーホッホ』『むぎばたけ』『あめのひ』『あまがさ』『ピーターのてがみ』 |
 |
『本を選ぶ目を養うために(三)』 2008年9月20日(会報第51号) 津山市で3日に渡って開かれた選書セミナーの報告/ ノートルダム清心女子大学付属小学校でゼミの学生が行っている物語の読み聞かせの事例報告(『ふたりのロッテ』を中心に)/ 選書セミナーに際して開発した、朗読を交えて十分間で長編を紹介する方法/ その方法を使っての本の紹介 『飛ぶ教室』『オタバリの少年探偵たち』 『ゲラダヒヒの星』『ニルスのふしぎな旅』 |
 |
『本を選ぶ目を養うために(四)』 2009年1月24日(会報第53号) 誕生日や手紙をテーマにした絵本や物語を取り上げた。 他者の心を読む能力の発達について、事例を挙げての説明(湯澤) 内緒で誕生日のお祝いの準備をするという内容の絵本の比較/ 手紙と誤解にまつわる絵本の比較/ 手紙が重要なモチーフになっている物語の比較/ 『赤毛のアン』の最高にうれしいプレゼント/ 『親愛なるブリードさま』/ まとめの話(脇) 『ピーターのてがみ』『思い出のマーニー』 『まぼろしの小さい犬』『百まいのドレス』『牛追いの冬』 『点子ちゃんとアントン』 |
 |
『子どもの自尊感情を育てる絵本・物語』 2009年7月11日(会報第56号) 「岡山子どもの本の会」では、特別支援を必要とする子どもたちにどんな絵本が助けになりうるかについて、調査研究中だが、その過程で見えてきたのが、自尊感情を尊重することの重要性。 自尊感情についての基礎的な話(湯澤)/ 自尊感情を育てる絵本・物語の紹介 (事例の紹介や、問題のあるものとの比較を交えて) 『くまのコールテンくん』『ラチとライオン』『コッコさんのおみせ』 『番ねずみのやかちゃん』『あくたれラルフ』『どろんこハリー』 『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』『ねことおんどり』『こぐまのくまくん』 『なあくんとちいさなヨット』『カイサとおばあちゃん』『コネマラのロバ』 |
 |
『本を選ぶ目を養うために(五)』 2009年10月10日(会報第56号) 盗みをテーマとする絵本や物語を取り上げた。 テーマの説明(脇) 昔話の紹介:『世界のはじまり』の中の「うけとれ、走れ!」 『白いりゅう黒いりゅう』の中の「犬になった王子」 『かしこいモリー』『北風のところ行った男の子』/ 『ふたごの兄弟の物語』『海の島』 まとめの話 |
 |
『本を選ぶ目を養うために(六) しつけ絵本を考える』 2010年1月23日(会報第58号) しつけ絵本を求める声が高まっているが、疑問を感じる絵本も多い。 問題提起と良い本との比較(梶谷) 道徳性の発達と絵本(湯澤) 子育ての経験から 子どもたちに挨拶などの生活習慣をつけさせなければならない立場から 保育士の立場から 家庭文庫の経験から 『番ねずみのヤカちゃん』の、しつけ絵本という観点からの考察 まとめの話(脇) |
 |
『子どもに本を手渡すには』 2010年5月8日(会報第60号) 4月のストーンさんの講演会を聞かれ、「やなぎむら」シリーズはとてもいいけれど、絵が細かくて集団の読み聞かせにはむかないと思っていたが、大丈夫らしいとわかった、という声があったで、まずこの問題について検討した。 子どもは小さいものをよく見ている。 幼児の視力 集団相手の「やなぎむら」シリーズの読み聞かせ 大型絵本の問題点 はじめての子どもたち相手の読み聞かせでも、絶対確実な方法 中学生たちに物語の本を手渡す方法と、いまの中学生たちが最後までちゃんと読んだ推薦図書(小幡) |
 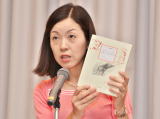   |
岡山子どもの本の会選書セミナー『家庭読書への道案内』 2010年9月11日(会報第62号) 「岡山子どもの本の会」では、2008年度と2009年度に、岡山県教育委員会の委託を受けて、津山、総社、赤磐で選書セミナーを行いましたが、その成果を活かして行くために、岡山県立図書館で選書セミナーを実施しました。 「家庭で物語の朗読を」(脇) 絵本の読み聞かせだけでは読書につながらない。小学校になって自分で読み はじめても、いいかげんな本の流し読みではなんと力にもならず、それよりも、 大人がいいものを選んで朗読して聞かせ、想像力や思考力が働く物語体験をさせる ほうが、ずっと意味がある。 「親と子がいっしょに笑える本」(尾島) 『あくたれラルフ』『番ねずみのヤカちゃん』『ものぐさトミー』『なあくんとちいさなヨット』 『がんばれヘンリーくん』『点子ちゃんとアントン』 「お父さんが照れずに読める本」(近藤) 「シートン動物記」の『レイザーバック・フォーミィ』『ラギーラグ』『バナーテイル』 「河合雅雄の動物記」の『カワウソ流氷の旅』と『極北をかけるトナカイ』 『小鹿物語』『世界のはじまり』『カマキリと月』『ニルスのふしぎな旅』 「生活力をアップさせてくれて、生きていけるという自信のつく本」(片平朋世、小野田) 『農場の少年』 『チムとゆうかんなせんちょうさん』『ラチとらいおん』 『せきたんやのくまさん』『パンやのくまさん』などのくまさんシリーズ 『スモールさんののうじょう』などのスモールさんシリーズ |
 |
『本を選ぶ目を養うために(七) 笑いとユーモアを考える』 2011年1月22日(会報第64号) テーマの説明 子どもの本には、楽しいユーモアで元気をくれるものがたくさんあるけれども、 その一方で、「子どもに受ける」と人気の高い本の中には、こんなことで 笑っていいのかと不安になるような「見下す笑い」もある。 「笑い」にもいろいろあるので、それを見極める目を持てるようになりたい。 心理学の立場から子どもの笑いについての解説(湯澤美紀) 笑いの発達について、年齢を追って説明。 「昨日の自分を笑う」 『三つ子のこぶた』『きかんぼのちいちゃいいもうと』『小さなジョセフィーン』 エーミールのいたずら325番』『エーミールと小さなイーダ』『 「視野がぱっと開ける笑い」 『かばくん』『けんた・うさぎ』『王さまと九人のきょうだい』『ずいとんさん』『わたし』 「人とつながる喜びの笑い」 『パンのかけらとちいさなあくま』『たんじょうび』『チムとゆうかんなせんちょうさん』 『きみなんかだいきらいさ』 「自分のスタイルで生きる人がかもしだす笑い」 『なあくんとちいさなヨット』『番ねずみのやかちゃん』『800番への旅』 笑える本のきわめつき(脇明子) 『シェパートン大佐の時計』『ハイフォースの地主屋敷』『シーペリル号の冒険』 |
     |
『生きる力を育てる絵本と物語』 2011年7月2日(会報第65号) 5月と6月にあいついで発行された『子どもの育ちを支える絵本』と『自分を育てる読書のために』のことを中心に、本をまとめくなかで見えてきたことや、書き切れなかったえ,ソードなどが紹介された。 『子どもの育ちを支える絵本』が、「散歩でいろんなことを体験すること」「遊んで遊んでおなかをすかせておいしく食べること」「たっぷりの愛情を安全基地として冒険に挑戦すること」の三本柱で構成されることになったいきさつと、おまけ事例。(梶谷恵子) 保育園の運動会でのレスキュー隊の話。(片平朋世) 今回のプロジェクトから学んだことについてのまとめ。。今回のプロジェクトでよかったのは、まず第一に「子どもの育ちを支える」という目標がぶれなかったこと。二つ目によかったのは、いろんな立場のメンバーが関わったこと。三つ目は、それぞれが子どもについて語ることで柔軟な方法を探っていけたこと、四つ目は、トップダウンのやり方でなく、それぞれの立場から共通の目標にむかって進んでいけたことだった。(湯澤美紀) 小学校での『ながいながい旅』(ヴィークランド)の読み聞かせの事例。 本で紹介した「ふたごの兄弟」の書き切れなかったエピソード、題して「ふたごが起こしたクリスマスの奇跡」のお話。(小幡章子) 何よりも大切なのは子どもたちが生きる力を身につけていくことであり、絵本も物語もその手段の一つだということを忘れないようにしたい。生きる力とはどんなものかを理解し、絵本や物語がその力を育てるのにどう役立つかを理解すれば、何を選べばいいか、どう手渡せばいいかということは、自然に明らかになる。(脇明子) 茶話会   |
| 岡山子どもの本の会選書セミナー 『子どもたちは生きる力をもとめている』 2011年9月3日(会報第66号) 「岡山子どもの本の会」では、2008年度と2009年度に、岡山県教育委員会の委託を受けて、津山、総社、赤磐で選書セミナーを行いましたが、その成果を活かして行くために、岡山県国際交流センターで選書セミナーを実施しました。これは岡山子どもの本の会独自の催しとしては、2回目なります。 「選書はなぜ大切か」(脇明子) |
|